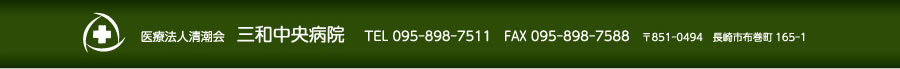| アーカイブ |
対談『心理職の果たす役割と看護との連携』
投稿日時: 2019-08-23
今年度より、心理療法室の森室長が、長崎県臨床心理士会の会長に就任されました。その一方で、これまで日本精神科看護協会長崎県支部を牽引されていた尾上看護部長が支部長職を退かれます。
そこで今回は、お二人に『心理職の果たす役割と看護との連携』として対談していただきました。
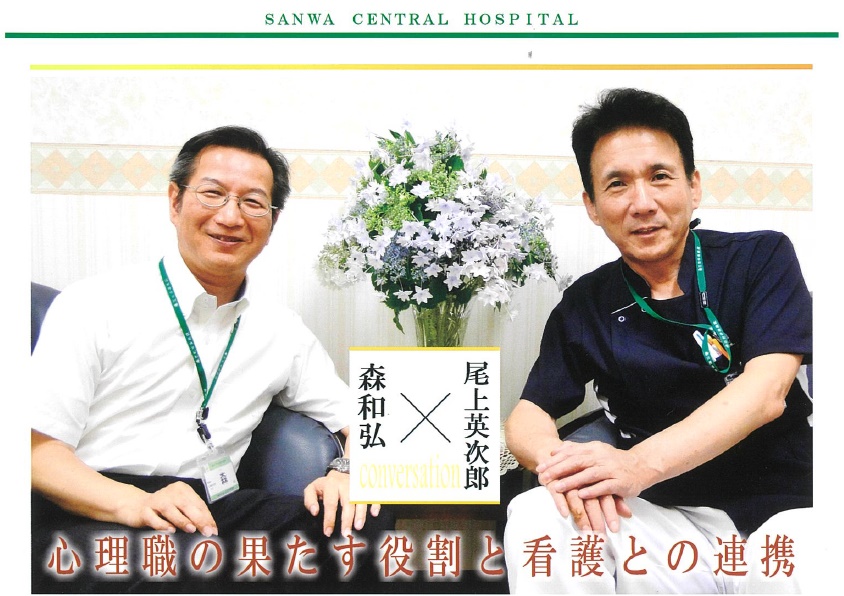
〜1. 精神科病院で心理職が必要とされること〜
心理職の大きな役目の1つとしては精神科医師の補助や手助けを担っているということです。医師も一人で患者を数十人と担当していくため、患者様の心理面を詳細に診察することは困難でした。そこで心理職が面接や心理検査を詳細に行っていくことで医師の負担を軽減していました。
そしてもう1つ、これは私が臨床の現場で実体験になりますが…当時私はアルコール依存症の病棟に配属となり、患者様の性格や病態を手探りで対応している状態でした。不明な点や対処法を医師に問うも、忙しくてつかまらないことがほとんどでした。精神科病院は医療法による人員配置では「医師数は患者48人に対し1人」と定めてあり、1日で数名を診察するだけでも手一杯の状況でした。当然、患者様も入院治療の不安、不満などの訴えが多くなり、その結果看護やコメディカルも多忙を極めていました。そんな中、心理職の方が患者様と面接をされて、その内容から「この患者様は過去にこういう辛い経験をされているから触れない方がいい」「こういう部分は話を聞いた方が良い」など、患者様に合わせた関わり方や対応ポイントを週1回の病棟ミーティングの中でスタッフへ提供していただき、そしてスタッフもミーティングの中で陰性感情等、対応した結果を共有、フィードバックすることで患者様とも良い関わり方を築くことが出来、非常に助かったことを良く覚えています。また看護師としての自己の看護観(気づき・振り返り)等、非常に勉強になり、今の自分があるのだと思っています。
全体として見ても心理職の存在は大きく、患者様が主治医に話しづらいことも心理職には話していただけるケースが多い。また主治医を中心とした医療チームの中で看護師やリハビリ部など各職種の強みを生かせるような言葉かけをいただき、医療チームとしての自信にも繋がっています。
>> 患者様と心理職間だけでなく、医師や看護師、他職種が上手く連携するための橋渡しのような存在なのですね。
尾上
また現代社会における一般的な重要課題として職場内での人間関係やストレスの問題があります。看護の離職の理由で第1位は人間関係です。やはり日ごろの関係づくりは大事だと思いますし、一般職員はもちろん指導者にあたる師長・副師長にも当然ストレスがかかるものだと考えています。そこで心理職に師長・副師長勉強会に参加していただき、働く側のメンタルもケアして頂ければと考えています。私自身も勉強になっております。
最近は一般科の看護部長さんも倫理、対人関係、メンタルヘルスについては課題であると、精神科病院での心理職との協働は高い評価をいただいています。
>> 尾上看護部長ありがとうございます。
森先生、心理職としてはいかがでしょうか。
森
尾上
森
今までの話でいうと、心理職の役割が見えてくるところがあって、患者様の理解をどのようにすればいいか、そして理解をどのように支援につなげるのか、その2つなのかなと思います。
特に前半の話ですと心理検査や面接をする中でどんなふうに感じたか、この患者様はこういう性格があるんじゃないか、患者様の性格をどのように理解し支援に応用していくかだと思います。
後半の話では医療チームの状況をどのように理解して人間関係とかそれぞれの立場を理解して患者様の治療に上手く活かすためにはどのような動きをすればいいか理解と支援に繋げるという役割だと聞いていて思いました。
尾上
例えば何かトラブルがあった時「何かしなきゃいけない」という思いが先行し、何もしていない自分への焦りから自分を責めたり自己嫌悪に陥りがちですが、そうした時に心理職から「今はいいんですよ。」「今は待つしかないんですよ。」ということを理論的にアドバイスいただき助かったところもありました。また特定の看護師の患者様への対応について相談された際も詳細を聞いたうえで「そういう方も居て良いんですよ」と共感するアドバイスをくださったこともありました。
森
精神科というのは他科に比べると患者様の病気とか症状とかコントロールしにくいですよね。外科や内科のようにはいかず、どうしても病気や症状が根強いところがあり、こちらもなかなかうまくいかない感じや、長く付き合っていかなきゃいけないしんどさが精神科にはありますよね。そういうスタッフ同士でのしんどさや患者様がなかなか良くならない、これでいいのかという、病気に対してのコントロール度の低さから「今はこれでいいんだろうか」と迷いを生むところがあります。
尾上
よく他科の看護師から「精神科の患者様はどんな対応をしたら落ち着く(治る)と?」と聞かれますが「いや、落ち着かんでしょ(笑)」とよく言っています(笑)「あんた達いい加減ね(笑)患者様のこと真剣に考えとっと?」と聞かれますが、それは如何に息の長い付き合い方をしていくかが、大事だとお答えしています。
森
寛解というのは治療を受けながらその状態をキープしていくということですから、慢性疾患ですよね。私も高血圧の薬を飲んでいますが、精神科の治療も同じようなことが言えます。どうしてもスパッといかないのが精神科なのだと思います。ではなぜ心理職が役に立つかですが、心理職の関わりは「治す」とは微妙に違うところがあって、その患者様が持っているものをどうにか「活かす」ように関わっていくことだと思います。
尾上
森
患者様が病気や現在の状況についてどのように感じているか、どういう理解をしているか、それによってこちらの働きかけも違ってきます。
例えばアルコールのインテークであればどちらかと言うとARPに乗っかってもらうような形で橋渡しをしますし、外来の心理療法や面接であれば具体的な目標を共有して進んで行きます。でもやはり患者様がどのように理解しているかとか、どこまで準備が出来ているかによって、こちらが何を提供するかの準備次第ですね。やりとりを重ねていくと準備がだんだんできたりします。
尾上
そうしたものがあることをまず理解することが大事ですし、それに伴う他部署との連携(人間関係作り・コミュ二ケーション能力)も大事だと思います。
「患者さんも何も言わないし、どこからも話が無かったので黙っていました」などではなく、患者様と24時間近くにいる看護師がある程度タイミングを計り他部署と連携できるような立ち回りが大事だと思います。その結果、患者さん、家族よりあなたが(看護師)、他の部署へ橋渡し(助言)をしてくれたお蔭で症状が安定しました。社会復帰ができ良かったですと感謝の言葉をいただくケースもありました。
森
尾上
〜2. 心理職とは〜
森
1つは、「人間全般の行動の法則を把握して、それを支援に活かす」方向。元々、心理学というのは人間の行動に関する法則を見出す学問なのです。それを支援を必要としている人たちやその関係者のために活かすわけです。
もう1つは一人ひとりがどのような人間でどういう世界に生きているのかを事細かに理解して、それを支援につなげていく方向。これは、臨床心理学や臨床心理士が重視してきたあり方です。
つまり、支援のあり方には全般的な方向と個別の方向の2種類があると思います。
臨床心理士という資格、これは一人ひとりを大事にしましょうという方向性を持った民間資格です。それとは対照的に今度出来た公認心理師は国家資格です。国家資格ということは国民全体の役に立たなければいけないという側面があります。公認心理師は、「国民の心の健康の保持増進」という、先ほどの職場のメンタルヘルスとつながるような、広く国民全体に情報・知識を提供することも求められています。
今まで心理職が活躍していた領域よりも、もっと広い分野で活躍する必要があります。
尾上
森
尾上
森
尾上
心理職は今後様々な領域に関わることが期待されています。
特に高齢者の分野には社会のニーズがあると、私は感じています。
森
地域で見ると精神疾患の老人あるいはご家族が精神疾患を患っている方は必ずと言っていいほどいらっしゃいますし、そうした方々を理解したいというものです。
精神科で学んできたことが地域の役に立っていると実感しています。
尾上
2025〜7年くらいまでは高齢の方が増えて行きますから、そうした活動に今後も需要が高まると思います。
森
こうした世の中のニーズの変化に心理職も対応の幅を広げていく必要があると感じています。
〜3. 専門職としての心得〜
尾上自分のスキルを磨くためにも自己啓発として職能団体に入り、病院という小さな組織からもっとマクロ的な世界を見ていくことが大事です。
自己啓発には時間や金銭の投資がつきものですが、それは経験となって必ず還元されます。様々な人と出会い、その中で自分の中のモデルとなる人を見つけることが出来ます。また専門職としてだけでなく人間として成長できるし、成長している人を見ることができます。
どの専門職でも同じですが、自己啓発がなければ自分の成長はないし企業も発展していきません。専門職であるならば職能団体に所属して知識・経験を積んでいくことが大事です。
私はよく「知識と経験を踏まなければ不安になる」と言っています。経験を踏んでおけばその時その時は上手くいかないかもしれないが、あるところまでなると感覚的な判断で分かるようになっていきます。また歳をとってから経験することは恥ずかしくてできないし、引っ込み思案になり、知識がなくて不安にもなります。
特に私たち看護師は取り返しのつかない命が関わる職業です。将来不安にならないためにも若い時からコツコツと知識を得ながら経験を積み重ねることが自分の力になっていくので、ぜひ職能団体に所属して頂きたいと思っています。
>> 尾上看護部長、ありがとうございます。
命という取り返しのつかないものが関わる環境の中で判断を求められる看護師だからこそ、若いころから職能団体に所属し様々な経験を積み重ねていくことが大事ということですね。
森先生はいかがでしょうか。
森
心理職で多いのが一人職場です。看護であれば十何人と居るので先輩がいて見て学んだりすることができますが、一人なので「これが合っているのか」ということすら分かりません(笑)
そこで「これでいいんだ」と思ってしまうと独りよがりになってしまい、それは絶対患者様や支援を受ける人の役に立たないですね。ですので研修を受けることは大事ですね。卒業したての頃は特にいろんな方と関わった方が勉強になりますので、私も職能団体に所属することをお勧めします。
特に若い時に一緒だった方は今でも付き合いがありますし、ネットワークが全国に広がります。その点が一番大きいと思います。また、臨床心理士は5年更新の資格です。その間に、必要な研修を受けないと更新できず、臨床心理士でいられなくなります。これが臨床心理士の特徴だと思います。
尾上
〜4. 今後の展望〜
尾上それに伴い医師はもちろん、コメディカルはより専門性の高い技術が求められようとしています。
私の展望としてはコメディカルとしての知識・技術・経験を今のうちに積み重ねて欲しいと思っています。そして三和中央病院が患者様に選ばれるようにチーム一丸となって頑張ってもらえたらと思っています。もちろんこれは看護だけに限った話ではありません。リハや栄養、もちろん事務職の方も専門性はあります。そして最終的にはどこかで患者様と繋がっています。つまりみんなで患者様を看ているのです。患者様を良くしたいという考えが統一できれば、1つのチームとして部署間の連携も上手くいき、病院も発展していくと考えています。
>> ありがとうございました。
最後に森先生お願いいたします。
森
今までの臨床心理士の民間資格に加えて新たに公認心理師という国家資格ができました。
そんな心理職がチームとしてどんなふうに役に立つかですが、まず何にしても常勤の人が少なく、非常勤の方が多いというのが実情です。そのためまずは臨床の場の安定がまず大事かなと思っています。そして国家資格になったことでいろんな分野で活躍して国民に還元していければと思っています。
尾上
森
また制度といいますか、診療報酬においては、さまざまな形で位置づけてもらえるように、これまで以上に全国の職能団体と連携して働きかけていきたいと思っています。
国家資格化を機に入れてもらって一定の役割を果たし、活動の場が広がり、心理職の地位の確立の役に立てればと思っています。
また長崎県臨床心理士会では、すでに県や市町のさまざまな審議会や委員会に委員を派遣して意見を述べさせていただいているのですが、そうした活動も今後活発になっていくと期待しています。
>> ありがとうございました。
本日は、お二人には貴重な時間をいただきありがとうございました。
- 【Webのみ開催】令和3年度長崎県アルコール依存症診療ネットワーク講演会 (2022-01-18)
- 断酒例会(オンライン)のご案内 (2021-08-12)
- 断酒例会(オンライン)のご案内 (2021-07-02)
- 断酒例会(オンライン)のご案内 (2021-03-12)
- 【紹介】くらしとこころの総合相談会 (2021-03-06)
- 断酒例会(オンライン)のご案内 (2021-02-12)
- 家族会の開催中止について (2021-01-14)
- デイケア販売会のお知らせ (2020-10-26)
- デイケア家族教室中止のお知らせ (2020-08-14)
- 家族会の開催中止について (2020-07-08)
- 家族会の開催中止について (2020-05-08)
- 家族会の開催中止について (2020-03-02)
- 第9回よかよかの会, 第84回さんさん会 のご案内 (2020-01-17)
- 第8回よかよかの会のご案内 (2019-11-24)
- 第83回さんさん会(家族会)案内 (2019-11-18)
- 第4回地域交流祭りのご案内 (2019-10-15)
- 第7回よかよかの会, 第82回さんさん会 のご案内 (2019-09-20)
- 対談『心理職の果たす役割と看護との連携』 (2019-08-23)
- 第6回よかよかの会, 第81回さんさん会 のご案内 (2019-07-22)
- 第5回よかよかの会(家族会) (2019-06-10)